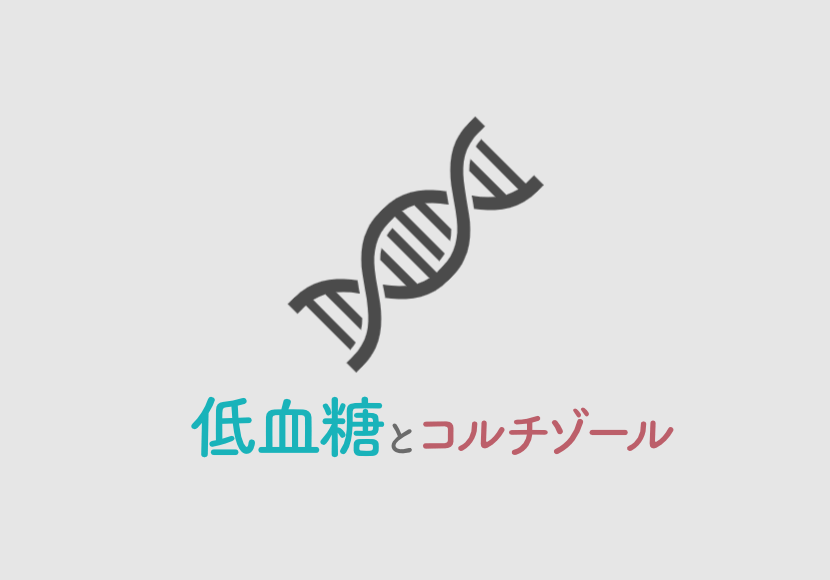中学生くらいから長年「低血糖症」です。
対策としては「糖質制限」がよく挙がるのですが、
「副腎疲労」を併発している場合は、そう簡単にいかない事情がありました。
もくじ
低血糖症が発覚したら「副腎疲労」も疑うべし
「低血糖症」と「副腎疲労」は併発していることが多いです。
基本的には「副腎疲労」の対策をすると「低血糖症」の改善にもつながります。
「低血糖症」って何? という方のために、ざっくり説明すると、
「低血糖症」は空腹時がつらい
低血糖症は「食事の有無」でメンタルが左右されて、体調の変化が劇的になりがちです。
- 午後3時〜4時頃に急激な眠気
- 夕方頃、夜の10時頃に体がフラフラする
- 手足に力が入らず震えがくる
- お風呂で立っていられない
- ドライヤーで髪を乾かすのに立っていられない
- 空腹が耐えがたくイライラする
- 食事を摂ると今までの症状が嘘のように元気になる
- 悪夢をよく見る
- 滝のような寝汗をかく
普段は穏やかな性格なのに、空腹になるだけでかなり機嫌が悪くなったり気分が沈んでしまいます。
そして食事を摂るとケロッと治ってしまうのが特徴です。
「副腎疲労」は心と体のグッタリ感がはんぱない
一方、「副腎疲労」は、とにかく何をするにも「だるおもー……」な状態です。
- 朝起きられない
- 疲れが取れない
- PMS(生理前症候群)の重症化
- 性欲低下
- 夕方頃に疲れがひどくなる
- ケガや風邪が治りにくい
- 何に対しても楽しみを感じられない(抑うつ状態)
- 同じことをするのに以前の何倍もの努力が必要
空腹だろうがなんだろうが、一日中ひどく疲れていて、その疲れが長期間続いてしまいます。
そもそもなんで「低血糖症」「副腎疲労」になっちゃうのか?
ストレスが副腎の許容量を超え、適応できなくなったから です。
副腎は、ストレスに対応するためのホルモン「コルチゾール」を出すところ。
ストレスが心と体に降りかかると、副腎は「コルチゾール」を出して心と体を守ろうとします。
しかし、回復の間もなく次のストレス、また次のストレス……
たとえ小さなストレスでも、積み重なって副腎が疲弊していったわけです。
そして副腎は「血糖値を正常に保つ働き」も担当しています。
よって、副腎が疲労すると血糖値を正常に保てない = 低血糖症も併発
というわけです。
「低血糖症」「副腎疲労」の対策は?
- コルチゾールの無駄遣いを減らすこと
- 栄養をきちんと消化、吸収できる体を作ること
「コルチゾールの無駄遣い」は、具体的には「ストレスを減らす」のが大事です。
「消化、吸収」は、今まで食事を摂っていたのに、ちゃんと栄養にできていなかった可能性があります。
臓器の疲弊も、ホルモンの出力も、土台は栄養。
そのためには「消化、吸収」が大事です。
「低血糖症」の対策で多いのは「糖質制限+高タンパク食」
そもそも「低血糖症」は、血糖値の乱高下でも起こります。
糖質過多の食べ物を摂ると、血糖値が爆上がりしますよね。
それを抑えるためにインスリンが分泌されて、今後は爆下がりします。
健康な人は、ほどほどに上がって、ほどほどに下がるのですが、
極端に上がって、極端に下がる人もいるのです。
このジェットコースターみたいな血糖値の乱高下、「下」のときに「低血糖症」の症状が出ます。
ならば、
「症状が出ないようにするには、糖質を食べなければいいじゃない」
という考え方が出てくるのも当然。
その場合、「糖質過多+タンパク質不足」が土台にあるという考え方なので、
「糖質制限+高タンパク食」が基本になります。
エネルギーはどこから摂るの?
という疑問には、「糖新生」を答えとして差し出したい。
糖は、タンパク質や脂肪からも作れるのです。
それを「糖新生」と呼びます。
(肝臓で行われます)
なので、人間の体は「絶対に糖質を摂らなければいけない!」わけではないのです。
さらに、「ケトジェニック・ダイエット」として有名ですが、
脂質もエネルギーとして使えるように体を作り替えていく、という手もあります。
くわえて、タンパク質や他の栄養素は基本的に不足しているので、
- プロテインを飲む
- お肉、魚、チーズ、卵を増やす
- エネルギーを脂質由来に切り替えたいから脂質を増やす
- ビタミン、ミネラルをサプリで補充していく
こういった流れになります。
副腎疲労がなく、もともと健康でダイエット目的の人なら「糖質制限+高タンパク食」でいいのです。
副腎疲労の人が「糖質制限+高タンパク食」だと逆効果
食事で血糖値が上昇し、徐々に下がってくるのは健康な人と同じです。
ですが、副腎が弱っていると、「コルチゾール」の出力が弱くなります。
タンパク質と脂質を使って、肝臓が「糖新生」をするのが難しくなります。
さらに肝臓は、保管していた貯蔵血糖(グリコーゲン)を血糖(グルコース)に変換することもできるんですが、それも難しくなってしまい、
血糖値がどんどん低下していってしまう。
すると、体に力が入らない、フラフラする……「低血糖症」が悪化してしまうわけです。
そもそも、副腎疲労や低血糖症でお悩みの方は、高タンパク質、高脂質に耐えられる胃腸じゃないことが多いので、
栄養を消化吸収できていない → いくらプロテインを飲んでも栄養にできない
となります。
さらに、高タンパク食は消化の負担が増えるので、
そのストレスに対応するために「コルチゾール」を使ってしまう……
悪循環にハマってしまうわけです。
副腎疲労で低血糖症の人(自分)はこうすればよかった
良質な炭水化物を摂取すればよかった
糖新生はあてにならないわけですから、「断糖、完全糖質オフ」ではなく、
血糖値がゆるやかに上がる炭水化物を摂っていれば、最低限の血糖値はキープできます。
とにかく動くのがだるいなら、昨今言われている糖質の悪影響は一旦おいといて、
まずは動けるようになるのが最優先と考えます。
- さつまいも
- かぼちゃ
- 栗
- 押麦ごはん
- 雑穀ごはん
などですね。
食事のときに少量摂って、間食としても少量摂れば、血糖値が下がりすぎるのを予防できます。
オフする糖質としては、
お菓子や小麦系(パン、パスタ、うどん、そば)、白米、乳糖、ジュース(果糖ぶどう糖液糖)を減らすだけで十分でした。
補食を摂ればよかった
食事の間が4、5時間とか空いちゃうと、血糖値が下がりすぎてしまいます。
間食というとお菓子のイメージが強いですが、
血糖コントロールの場合は「補食」と呼ぶのが一般的です。
さつまいも、冷えた押麦ごはん(塩昆布まぜ)、栗、干し芋、ナッツなどがオススメです。
栄養を足すより先に「消化酵素」の助けを借りればよかった
「低血糖症」「副腎疲労」の人は、消化能力が低下している人が多いです。
そもそも消化能力が低下しているから、栄養不足に陥ってホルモンが弱体化したり、臓器が疲弊したり……
という要因が大いにあります。
単純思考で、
「タンパク質足りないからプロテイン飲もう!」
も、アリなのですが、
そこはちょっと落ち着いて、
- なぜ栄養が不足していたのか
- なぜ栄養を届けられていなかったのか
を考えるべきです。
だいたいは、
- 胃酸不足
- 消化酵素不足
- 腸内環境の悪化
が答えになりますので、
- 胃酸補充
- 消化酵素
- プロバイオティクス
の助けを借りましょう。
栄養の量だけでなく、受け入れる側の問題をもっと深く追求すればよかったわけです。
オススメの消化系サプリメントについては、こちらに詳しく書いてあるのでぜひ!↓

塩水をもっと摂るべきだった
体調不良の根本原因は「隠れ脱水!」という言説も、よく見かけるようになりました。
しかし意外や意外、水だけだと実はダメでして、「カリウム」が過剰になりがちです。
「低血糖症」にとって「カリウム」はちょっとやっかいな存在なので、
シーソーの関係である「ナトリウム」を多く摂ることで「カリウム」を抑える必要があります。
「ナトリウム」は塩から摂れるので、水を飲むときは塩を混ぜましょう。
朝いちでコップ一杯の塩水を飲むと、午前中の体の軽さが違います。
入れる塩は「ぬちまーす」がオススメ。
(マグネシウムが世界一豊富です☟☟)
ストレス過剰の環境から逃げるべきだった
「副腎疲労」は、知らず知らずのうちにエネルギーを消耗して発生するため、
心身を疲弊させる「エネルギー泥棒」を見つければ、副腎を守れます。
他人を優先しがちな「他人軸」の人は「自分軸」に切り替えたり、
自分の思っているより数倍多く休んだり、
自分の思っているより「自分はあまり動けない」と自覚することだったり、
言いたいことやりたいことを抑え込まない、というのも重要です。
それが一番大変なんだよ!
という方にオススメなのはこちら。
『いやな気分よ、さようなら』は認知の歪みが網羅されている本で、
認知行動療法については他はもう読まなくていいやってくらいの内容です。
そして note の方は、「他人軸」の人が「自分軸」に切り替えたいときに、
「嫌われてしまうのでは」という怖さをどう処理するか、を徹底的に掘り下げてくれています。
アドラー心理学も自己啓発書も全然効果なかった……という方はこれらを参考にしてみてください。
ちなみに私は、家事がやりたくないので、モノを徹底的に減らして家事を簡略化させたり、
要らない服や雑貨をがんがん手放し、超絶ミニマムな生活にして決断疲れを減らしたり、
知り合いの誘いを断りまくって対人関係をシンプルにしたり、
結構ハードな断捨離に取り組みました。
やりすぎるとストレスになりますが、もともと禅的な空間に憧れがあったので結果オーライです。
心と体は繋がっているので、というか全部ひっくるめて自分のカラダなので、
ストレスの考え方は「コルチゾール」に直結する、副腎という「臓器」に直結する、ということを忘れないようにしたいところ。
健康の問題に対しては、評価遅延学習になりがち
人生でぶちあたる問題で、解決策を学ぶのは後手後手になりがちです。
というかそれが普通ですよね。
「必要になった時に必要なことを学ぶ」
これを評価遅延学習と呼びますが、
デメリットは、後手後手であるということ。
メリットは、改善させたくて必死なので吸収率がいい、ということです。
少しでも先手をとって改善に繋げるなら、「情報収集」が武器になります。
主に、
- 自分に関する情報
- 治療に関する情報
の2つです。
自分に関する情報については精密検査が必要になりますが、大抵はものすごいお金がかかるので、日誌をつけるのが最重要になります。
(というか、働けば検査代支払るけど、副腎疲労で動けないから働けない、というジレンマはありますよね……)
症状に関する情報については、
- 書籍
- 論文
- ブログ
- YouTube
あらゆる情報が手に入る時代ですから、どんどん吸収していきましょう。
「評価遅延学習なのは当たり前!」として嘆かず、今できることをまずはやっていきます。
参考文献